「小説の神様」は、中学生でプロデビューした小説家の男子高校生と、もう一人のプロの女子高校生が二人で小説を書く物語である。
主人公の一也は、ネクラで、後ろ向きで、本も売れなくて、常に自己嫌悪と戦っているような存在。対してヒロインの詩凪は美人で、常に周りに明るく、本も飛ぶように売れており、非の打ち所なんて無いような存在。
物語はこの二人の対比を中心に描かれ、他のサブキャラクターとのやりとりも通じて、二人は二人でひとつの小説を書き上げていく。
この本のポイントは、何といっても「職業作家」というものを取り巻く現状を、小説というフィクションの中ではあれど、かなりリアルに描写している点である。
「新人賞でプロデビュー」「印税収入」といったイメージが先行しがちな出版・小説業界において、その実態はどうなのか、例えば印税収入はいくらなのか、何部売れればまともに生活ができるのか、作家と作家の関係はどうなのか、作家から見た「編集」とはどういう存在なのか、今の出版不況とは具体的にどういう不況なのか……そういったことが、デフォルメされながらもしっかりと描かれている。
主人公の一也はとにかく利益主義の作家だ。なにしろ売れる小説を書かないと食っていけない。そのためには、自分の信念や初心を忘れてまでも、売れる小説を書くことを重視する。しかし、書けない。書ける精神状態にならない。書けるようになったとしても、作家としてそれが許されない……そんな苦悩が、この作品には詰まっている。
この作品は、そういう意味で巨大な「作家あるある」だと感じる。世の中で暮らしている作家の多くはこれに共感できそうだ。しかし一方で、普通の読者にとってはどうだろう。「何だコイツ、ウジウジしてて面白くねえな」と思うかもしれない。
ストーリーについても、この「作家あるある」を除くと単純なボーイミーツガールもので、あっと驚く展開もなく、プロットレベルでは話が淡々と進んでいってしまう。キャラの感情描写をあまりにも重視するがために、ストーリーが犠牲になってしまった感は若干否めない。
ただ、読後感は悪くないのと、作家を目指している人であれば一度は読んでほしい作品でもある。なにより、作家がどのぐらい物語を愛しているのか、それがひしひしと伝わってくる。
Amazonのレビューも参考にされたし。
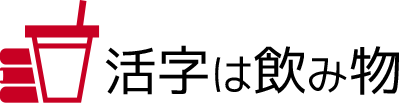






最近のコメント