「宇宙飛行士になりたい」という夢は、男子なら誰もが抱いたことがある夢だろう。本作品の主人公レフも、そんな夢を捨てきれずに宇宙飛行士の厳しい訓練に耐えていた。 レフはある日、宇宙に打ち上げる「実験体」として、「吸血鬼」を採用するため、その「実験体」の世話をするよう命令をうける。恐怖するレフだったが、実際に目の前に現れた吸血鬼は、自身の吸血鬼のイメージを打ち砕く、17歳の可憐な少女、イリナだった。 イリナは人間に憎しみを抱いていたが、レフの誠実さに徐々にその心を溶かし、二人は人間と実験体という関係を越えて結ばれていく――。 本作品は、1950年代(冷戦真っ只中!)のソビエト連邦をモチーフとした架空の国「ツィルニトラ共和国連邦」における宇宙開発に翻弄される青年少女を描いたものだ。当時のソ連はアメリカと宇宙開発競争を繰り広げており、その中には「ライカ犬」(地球軌道を初めて周回した犬、ただし宇宙空間で息絶えた)のような悲劇も数多くあった。 物語では、共和国の強引な政策とイリスへの冷酷な仕打ち、一歩間違えれば粛清が待っている緊張感と共に、イリナを宇宙空間へ打ち上げるための様々な訓練が描かれる。 とはいえこの作品、一冊分にそういったモチーフを盛り込みすぎているがため、とにかく尺が足りていない。 ロケット打ち上げまでに必要な訓練風景の描写、様々な登場人物たちの思惑等を描いているが故に、非常に広く浅くなってしまっているのが残念なところだ。 例えば、主人公を買ってくれている上官のコローヴィスは、事あるごとに彼に助け舟を出してくれるのだが、広く浅いが故にその行動理由や思想が伝わりづらい。 一方で、近年増えてきたチート、ハーレムなどの要素を排除し、国という大きな存在に対して、無力な二人が惹かれ合うという展開は純粋に見ていて美しいとも感じる。吸血鬼が好きな人、宇宙が好きな人は一度読んでみるといいだろう。 ……と、そんなことを言っていたら、なんと続刊が出るとのことらしい。あらすじなどを見る限り、続刊から物語が本格的にスタートしそうな気配もあるため、引き続きこの話は追ってみたい。
管理人の評価
- 2017.03.01
吸血鬼ヒロインに萌える……感想:白米良「ありふれた職業で世界最強」
「ありふれた職業で世界最強」は、突如異世界転生した最弱の主人公が、「地球に帰りたい」という想いを胸にどんどん強くなっていく、いわゆる異世界転生モノのライトノベルだ。
魅力的なヒロインと出会い、その世界でも規格外の能力を発揮していく様はまさしく「チーレム」なのだが、本作品の大きな特長は、その規格外の能力を得るまでの過程にある。
主人公のハジメは、オタクとして馬鹿にされ、スクールカーストでも底辺を生きていた。それが突如として異世界に召喚され、さぞかし高い能力を付与されるかと思えば、そんなことはなく。
ステータスは軒並み「10」と一般人並。しかし、他のクラスのメンバー達はみんな1000以上のチートスキルを持っている。そしてハジメは、とある事故がきっかけで、訓練場所だった迷宮から”奈落”へと落下してしまう。
クラスメイトの誰もが「ハジメは死んだ」と思っていたが、そうではない。実は彼は生きていた。しかも、”奈落”において生きるための超絶なスキルを身につけながら――。
超絶なスキルを身に着けたハジメはとにかく強い。そして何より信念がある。その信念は三つ。
「地球に帰ること」「愛する者を守ること」「その邪魔をする者は容赦なく殺すこと」
この信念は長い作品の中で終始一貫しており、揺らぐことがない。それ故か、この作品には全体を流れる安定感のようなものが確かに存在している。
第一巻では、ハジメが奈落に落ち、いかに絶望し、そして生きる術を身につけたかが描かれる。Amazonのレビューでも「気持ち悪い」と言われているだけあり、その内容は決して気持ちのよいものばかりではない。
だがそれでもあえて言いたいのは、この作品は「吸血鬼ヒロイン」に萌える作品だということだ。なぜ吸血鬼ヒロイン萌えなのか、それは一巻を読んで確かめてほしい。
ちなみにこの作品、Web版では完結しているので、放置の多いこのジャンルでは非常に珍しいともいえる。完結しているというだけでも読む気が起きる人は少なくないはずだ。
管理人の評価
- 2016.07.06
職業芸術家の苦悩が詰まっている。感想:相沢沙呼「小説の神様」
「小説の神様」は、中学生でプロデビューした小説家の男子高校生と、もう一人のプロの女子高校生が二人で小説を書く物語である。
主人公の一也は、ネクラで、後ろ向きで、本も売れなくて、常に自己嫌悪と戦っているような存在。対してヒロインの詩凪は美人で、常に周りに明るく、本も飛ぶように売れており、非の打ち所なんて無いような存在。
物語はこの二人の対比を中心に描かれ、他のサブキャラクターとのやりとりも通じて、二人は二人でひとつの小説を書き上げていく。
この本のポイントは、何といっても「職業作家」というものを取り巻く現状を、小説というフィクションの中ではあれど、かなりリアルに描写している点である。
「新人賞でプロデビュー」「印税収入」といったイメージが先行しがちな出版・小説業界において、その実態はどうなのか、例えば印税収入はいくらなのか、何部売れればまともに生活ができるのか、作家と作家の関係はどうなのか、作家から見た「編集」とはどういう存在なのか、今の出版不況とは具体的にどういう不況なのか……そういったことが、デフォルメされながらもしっかりと描かれている。
主人公の一也はとにかく利益主義の作家だ。なにしろ売れる小説を書かないと食っていけない。そのためには、自分の信念や初心を忘れてまでも、売れる小説を書くことを重視する。しかし、書けない。書ける精神状態にならない。書けるようになったとしても、作家としてそれが許されない……そんな苦悩が、この作品には詰まっている。
この作品は、そういう意味で巨大な「作家あるある」だと感じる。世の中で暮らしている作家の多くはこれに共感できそうだ。しかし一方で、普通の読者にとってはどうだろう。「何だコイツ、ウジウジしてて面白くねえな」と思うかもしれない。
ストーリーについても、この「作家あるある」を除くと単純なボーイミーツガールもので、あっと驚く展開もなく、プロットレベルでは話が淡々と進んでいってしまう。キャラの感情描写をあまりにも重視するがために、ストーリーが犠牲になってしまった感は若干否めない。
ただ、読後感は悪くないのと、作家を目指している人であれば一度は読んでほしい作品でもある。なにより、作家がどのぐらい物語を愛しているのか、それがひしひしと伝わってくる。
Amazonのレビューも参考にされたし。
管理人の評価
- 2016.07.02
安心して読める王道学園ミステリ。感想:「鉢町あかねは壁がある」
高校を舞台とした青春系のライトミステリ。写真部に所属する有我遼平(あるがりょうへい)と、中学時代からお互いに避け続けている鉢町丹子(はちまちあかね)の関係と、その周りで起きる事件についてを描く。
遼平は、幽霊部員の多い写真部で珍しく活動的に動いている生徒だ。丹子は校内で「スマイル」という名のつく占い師をやっており、タロットカードを用いた占いに定評がある。とはいえ、本当に占いの素質があるわけではなく、単にコールドリーディングのスキルが高いだけ。結構口が悪い。
だが、ひょんなことから遼平は、弓道部で起きた事件の真相について、写真部の部室で丹子と話すことになってしまう。ただし、丹子は暗室で、遼平はその外で。それがきっかけで、二人の奇妙な関係が始まった――。
本作品は学園系ラノベタッチのライトな推理小説だ。典型的な探偵役&ワトソン役で、探偵役が女子、ワトソン役が男子の構図。起こる事件は学内で起きうる日常的な事柄を取り上げつつも、疑問や問題提起を上手に煽りながら読者を作品世界に引き込んでいく。ライトなタッチとは裏腹に、伏線や登場人物はしっかりと回収されており、プロットの綿密さが伺える。
キャラクターの丹子はかなり濃い目のキャラに設定されており、根は大変口が悪い少女だが、状況によって色々な顔を使い分ける賢いヒロインでもある。ところどころで入る意味不明なセリフと、それに対する辛辣なツッコミを始めとした会話のコミカルさも良い。
そして、「遼平と丹子は面と向かって話せない」のである。丹子はとっさに目についた偽名を使い、壁を挟んで常に遼平から姿を隠しながら、遼平にバレないよう声色を隠して話し、遼平が出会った様々な事件を解決に導いていく。
帯にある「顔ばれしたら、終わっちゃうから、この関係」は、本作品の売りどころを凝縮したようなキャッチフレーズだ。重すぎず軽すぎず、楽しみながら読める一冊。オススメしたい。
管理人の評価
- 2016.06.27
感動系の作品だが構成に相当な難あり……「記憶屋(1)」感想レビューあらすじ
「記憶屋」という、誰かの記憶を消すことが出来る人間がいるという都市伝説を知った主人公の遼一は、自身の体験から、「都市伝説」が実は都市伝説ではないと感じ始め、「記憶屋」の正体を追い始める。その過程で起きる出来事を描いた話。
全体的に女子中高生向けといった印象かもしれないが、女子中高生が読んでも首をかしげるのではなかろうか。
キーパーソンを差し置いて別人物によるエピソードが途中で長々と入るため、ストーリーを追うのに手間がかかる。このエピソードが各キャラクターの理解を深めて感情移入する助けになれば良いのだが、出来事だけを消化しているために、結果的にキャラが薄っぺらい。また、1冊の中にテーマとなる話が複数乱立しているため、物語の構造を把握しづらい。
ただし「記憶屋」というテーマ自体は良かったのと、一応はキーパーソンの言っていることも理解できたのと、最後の1ページの説得力はあったので続刊も買う。
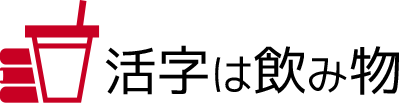



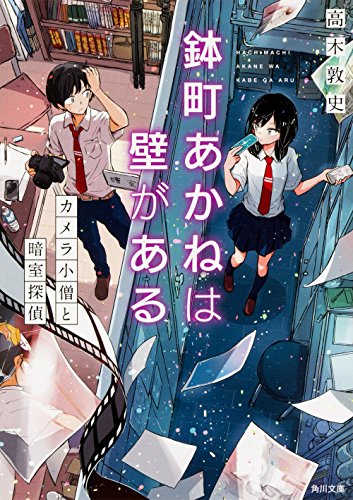




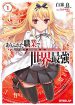

最近のコメント